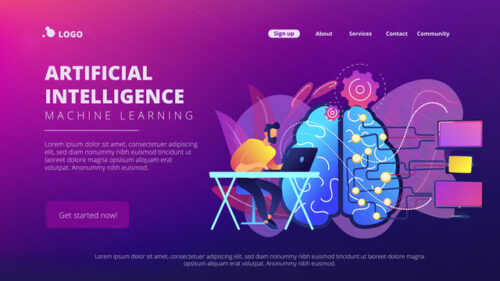2025年2月13日
「現在の学生がAIを学ぶ意義」第1回:AI教育の狭間世代が取り残されない為には
【寄稿】
[はじめに]
筆者が小学生の頃、1990年代にパソコンが一般普及され始め、2000年代にはパソコンが一家に一台、学校でもクラスに一台検索用のパソコンが配置されるなど、触れる機会が多くなりました。同じ時期にインターネットも急激に広がり、パソコン越しに広がる世界に強く興味を惹かれました。より深くIT技術を学びたいという思いから、専門学校でプログラミング技術を学び、システムエンジニアとしての道を歩み始めた。その後専門学校にて教員として若者の育成に従事。現在の会社に転職後、AIエンジニアとしていくつかのプロジェクトを経験した後、教育機関向けのAI教材開発を通して再び教育現場に携わっています。
これまでのキャリアを振り返ると、情報技術革新による社会環境の変化を目の当たりにし、それらを学ぶことの重要性を強く実感しており、教員としてもより最新の技術を教えることに意識を向けていました。現在、第四次AIブームとも呼ばれており、新たな技術革新の波が社会全体を変えてきていることは、皆さんも肌で感じているのではないでしょうか?
これまでの経験から現在の学生がAIを学ぶ意義をお伝えしたいと思います。
1.急速なAI技術の進化と社会浸透
2022年12月にChatGPTが登場し、わずか数ヶ月で1億人以上のAIユーザーを獲得。これまでのどんなテクノロジーよりも早く生成AIは世界中に浸透しました。ChatGPTの登場により始まったとされる第四次AIブームは、今までのAIブームとは比較にならないほどの早さで進化しながら社会に浸透しています。
2023年には生成AIの週次利用者が37%だったのに対し、2024年には72%に達しており、2023年時点では生成AIに対しての知識が薄かった金融や法律関連の職種に対しても、2024年には法律関係では58%、金融では70%と、AIの識者が急激に増えており、利用が広がっていることはデータから見ても明らかです。(※1)
2023年には多くの企業が生成AIの活用方法を模索し始め、2024年にはその取り組みが徐々に成果として現れ、AIによる効果が実証されました。これまで慎重に様子を見ていた企業も、様々な成功事例を参考にしながら導入を検討する動きが加速しており、今後はより多くの企業で導入されると考えられます。
AIはかつてのインターネットやパソコンと同じように、もはや情報技術を仕事とする専門家だけが扱う技術ではなく、誰もが使いこなすべきツールとなりつつあります。非エンジニア系のAI関連求人は2017年から2023年の間に5倍以上に増加しており、これまで技術職以外にあまり求められることのなかったAIスキルが、幅広い職種で必要とされています。(※2)
AIリテラシーが採用基準の一環として求められる場面は今後より増えていくことでしょう。
2.デジタル教育の狭間世代とネイティブ世代
AIの進化と社会浸透のスピードはパソコンとインターネットが一般普及した時代より早く進んでいます。少し前までは「AIは単なる流行りモノ」だと思っていた人も、今や文章だけではなく、画像や音楽、動画が作れるようになった進化の速度を目の当たりにしたら、考えを改めざるを得ないのではないでしょうか。
さて、パソコンとインターネットが急速に普及して一般化する中で、教育の現場では狭間の世代が生まれてしまっていた事をご存じでしょうか。2000年代以降、デジタル化が進むにつれて仕事でのパソコンスキルは必須となり、そのスキルが無いとキャリアの選択肢が狭まるという時代に突入しました。
1990年代後半から2000年にかけてのIT変革の過渡期において、教育の現場ではまだ十分な準備が整っていませんでした。しかし、2000年以降には小中学校でも急速にIT教育が進み、若年層のデジタルリテラシーは飛躍的に向上しました。この時期に生まれた子供はすでにインターネット環境が整った時代に幼少期を育ち、小学生時代にはパソコンや携帯電話といったデジタルデバイスが身近な存在として育っています。この「デジタルネイティブ」と呼ばれる世代が生まれた一方で、教育環境が整っていなかった1990年代後半から2000年にかけて学生時代を過ごした世代は、デジタル教育の恩恵を受ける機会が限られており、デジタルの分野において教育格差が生まれてしまいました。このような世代は「デジタル教育の狭間世代」とも言え、社会に出た後にデジタルスキルの不足が顕著に現れ、業務における生産性が低いという評価をされることになります。
このように急激な社会の変革時期に、「教育の狭間世代」が生まれてしまうことはAIが急速に普及する今の時代にも共通すると言えるでしょう。
3.AI過渡期と生まれる教育の狭間世代
AIが2022年をきっかけに大きく社会に浸透し、まさに現在はAI過渡期です。現在、日本ではICT教育、特に第四次産業革命スキルとなるIoTやAI教育に力を入れており、広く社会人や学生に向けた教育支援なども行なわれています。
文部科学省では「数理・データサイエンス・AI教育プログラム認定制度」という教育機関向けの認定制度を2020年度から実施しています。この制度はリテラシーレベルと応用基礎レベルがあり、AI時代に必要な知識を体系的に学べる環境を整え、社会で活躍できる人材を育成する事を目的とした認定制度です。リテラシーレベルはAIやデータ分析の基礎を学ぶもので、IT分野以外の学生も広く習得しておく必要があります。
2024年8月時点でリテラシーレベルが認定されている学校は391校(※3)です。2024年度に実施された学校基本調査では大学の数は813校(※4)となっているので、この制度を利用してリテラシーレベルの教育を行えている大学は半数にも満たない状態となっています。独自に教育を行なっている学校もありますが、IT系以外を専門とする大学や専門学校ではまだまだAI教育の準備が整っていない学校も多いのが日本の現状です。
2022年度から高校の授業で情報が必修化され、今年行われた大学入学共通テストでは初めて情報の科目が出題されました。高校ではITリテラシーに加えてAI教育も進み始めています。高校での取り組みに合わせて小中学校でも徐々に取り組みを進める動きがありますが、今後AI教育がより一般的になる事を考えると、現在の大学生や専門学校生は、まさに「AI教育の狭間世代」となってしまう可能性が大きいです。
4.AI教育の狭間世代が取り残されないためには
現在日本では少子高齢化に伴う、様々な職種で労働人口の減少が進んでいます。これを解決すべく、DXなどの動きが様々な業界で進んでいますが、一人あたりの生産性を求める動きが今後益々求められるようになるのは確実です。
大手インターネットグループであるGMOインターネットグループでは生成AIの活用により、2024年に合計業務削減時間が100万時間を突破したと発表しています。(※5)
また、ロート製薬株式会社でのプログラミング未経験の社員が生成AIを駆使してマクロを作成し、シフト作成を効率化したという事例も話題になりました。(※6)
昨年Windows11では大型アップデートで生成AIである「Microsoft Copilot」を標準搭載させ、Googleはスマートホーム製品である「Google Home」にマルチモーダルな生成AIモデルである「Gemini」を搭載すると発表しました。他にもAmazonもスマートアシスタントである「Alexa」に生成AI技術の導入を進めていると発表しています。身近なITデバイスに生成AIが続々と組み込まれ、現在幼少期を過ごす子供達は今後AIが身近に存在する「AIネイティブ世代」と呼ばれるような存在になります。
生成AIを活用した業務効率化の波は益々高まっていくと考えられます。今、大学や専門学校で学んでいる学生は、これから来るAIネイティブ世代と業務効率化の中で戦うことになります。
だからこそ、高等教育機関はいち早くAI教育の環境を整備し、一人でも多くの「AI教育の狭間世代」を減らす努力をすべきです。そのために、必要な情報はインターネットだけでなく、多くの企業が発信も行っています。本稿が日本の教育機関がいち早くAI教育の環境を整えるためのキッカケの一つになることを願っております。
※1:Growing Up: Navigating Generative AI’s Early Years – AI Adoption Report
※2:AI関連のエンジニア求人は6年で約4.7倍、管理部門など非IT系のAI人材募集も増加
※3:令和6年度「数理・データサイエンス・AI教育プログラム認定制度」の認定・選定結果
※4:2024年度「学校基本調査」速報
※5:GMOインターネットグループ、生成AI活用により2024年の合計業務削減時間100万時間を突破!
※6:プログラミング未経験社員がソースコードを生成し、シフト作成を効率化。文章生成や要約、翻訳など幅広い業務を効率化
◆執筆者
株式会社dott
AI教育事業部部長 市川 英将
 専門学校でプログラミングを学びエンジニアとしてキャリアを開始。その後、教員として情報技術を指導し、教員時代終盤は学科長として教育改革を推進。現在の会社に転職後、AI関連のプロジェクトを経験し、AI STUDIOの開発を開始。教員時代欲しいと感じていた、「教育者にとって使いやすく、活きた知識と技術が教えられる教材」を目指し、最新のAI技術を教育現場に届けるべく尽力中。
専門学校でプログラミングを学びエンジニアとしてキャリアを開始。その後、教員として情報技術を指導し、教員時代終盤は学科長として教育改革を推進。現在の会社に転職後、AI関連のプロジェクトを経験し、AI STUDIOの開発を開始。教員時代欲しいと感じていた、「教育者にとって使いやすく、活きた知識と技術が教えられる教材」を目指し、最新のAI技術を教育現場に届けるべく尽力中。
関連URL
<関連記事>
「AIと教育」第1回:AI技術が教育と社会に与えるインパクト
最新ニュース
- シンシアージュ、大阪・羽曳野市と子どもの学びと地域理解を推進する「包括連携協定」締結(2026年2月25日)
- VLEAP、中高生向け租税教育用デジタル版ボードゲームの制作に協力(2026年2月25日)
- 子どもの習い事、83%の親が「成長に合わせて選び方を変えるべき」=イー・ラーニング研究所調べ=(2026年2月25日)
- 令和の現役高校生は日常的にAIを使う。男女で大きな差 =ワカモノリサーチ調べ=(2026年2月25日)
- サイバー大学、学習歴と身分証を統合する次世代型「スマート学生証」を先行導入(2026年2月25日)
- 大和大学と奈良先端科学技術大学院大学、教育・学術分野の連携推進する包括協定締結(2026年2月25日)
- GMOメディア、ポータルサイト「コエテコbyGMO」で会話型プログラミング教室レコメンド機能の提供開始(2026年2月25日)
- 三英、STEAM教育スクール所属の中高生ロボティクスチームが「3冠」達成(2026年2月25日)
- 未踏社団、小中高生クリエータ支援プログラム「2026年度 未踏ジュニア」募集開始(2026年2月25日)
- ネイティブキャンプ、アプリ開発・起業教育プログラム「Technovation Girls 2026」に協賛(2026年2月25日)