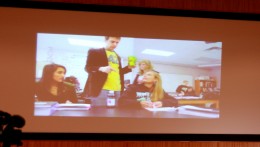2014年5月27日
FLIT/反転授業の先駆者が講演とワークショップを東大で開催
東京大学大学院情報学環・反転学習社会連携講座(FLIT)は、反転授業の普及に大きな役割を果たしてきたアーロン・サムズ氏を講師に迎え、「第2回 公開研究会」を24日に東京大学 情報学環・福武ホールで開催した。
米国の科学教師であるアーロン・サムズ氏は、当時同僚だったジョナサン・バーグマン氏とともに、2007年から米国コロラド州のウッドランド・パーク高校で動画を使った授業を開始。「Flipped Classroom(反転授業)」と名づけた授業は、メディアが取り上げて名前が一般に広まったという。
研究会では、アーロン・サムズ氏が講演とワークショップを実施。日本ではまだ知見の少ない反転授業について、先駆者の話が聞けるとあり、会場は満席になるほど多くの人が参加した。
アーロン氏は、反転授業の基本を、効率よくポイントを押さえたビデオを使い、授業の多くを実践に使うことと定義。加えて、「大事なのはビデオを使うことではなく、授業をどうするかということだ」と強調した。
自身の反転授業の様子を撮影した動画を紹介。教壇に立って講義をするのではなく、生徒の中を歩き回る様子が映し出された。これについて、「私が与えたい情報を与えるのではなく、生徒に何が必要か見ている」と解説。反転授業での教師の役割については、「学習プロセスを管理することが重要」とも述べている。
反転授業を実施する上で、デジタル格差を懸念する声もあると指摘。アーロン氏が教えていたコロラドの学校では25パーセントの生徒が、インターネットにアクセスできない状態だった。そこで、インターネット環境がない生徒にはフラッシュドライブを渡し、パソコンもない生徒にはDVDを渡すことで対応したと自らの体験を語った。
動画の制作についても解説。時間があまり長くすると生徒があきてしまうので、生徒の年齢が12歳であれば12分となるように、「生徒の年齢×1分」とした方がいいとアドバイス。また、インターネットからありものの動画を探し、組み合わせて利用するのもいいが、自ら作った方が自分の生徒や環境に合わせることができるとした。
聴講者からの、評価をどうすればいいのかという質問に対しては、授業中に生徒と会話しながら理解度を確認する、ビデオの途中に生徒に対する質問を入れてその結果を分析するなど、工夫をしていると答えた。
関連URL
最新ニュース
- ヘッドウォータース、東京都教委開催の「モバイルアプリコンテスト2025」を支援(2026年2月20日)
- ラインズ、茨城県龍ケ崎市で入退室管理システム「安心でんしょばと」一斉導入(2026年2月20日)
- 「教育機関の教員に対する生成AIの利用状況に関する調査 2026」協力依頼(2026年2月20日)
- 小中学生の「文系・理系」進路選択、保護者の7割以上が「特に希望はない」と回答 =LUXGO調べ=(2026年2月20日)
- 小学校入学、年長児保護者の84.5%が「不安あり」と回答 =ベネッセ調べ=(2026年2月20日)
- 金沢工業大学とNVIDIA、AI社会実装や高度情報技術者育成で学術連携協力協定締結(2026年2月20日)
- 中央大学、細胞診に即利用できるスタンドアローンAI診断支援システムを世界初開発(2026年2月20日)
- 九州大学、秀逸な若手研究者を採用する「稲盛フロンティアプログラム」第4期公募開始(2026年2月20日)
- 京都芸術大学、通信教育部がバークリー音楽大学・放送大学の一部科目を単位認定(2026年2月20日)
- mikan、西部台千葉高等学校における「mikan for School」導入事例を公開(2026年2月20日)