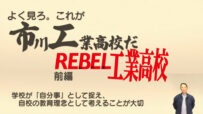2021年3月16日
本を多く読んでいる子ほど偏差値がプラスに =ベネッセ教育総合研究所調べ=
ベネッセコーポレーションの社内シンクタンク「ベネッセ教育総合研究所」は15日、小学生の読書に関する実態調査・研究の結果をまとめ発表した。
 同研究所では、進研ゼミの会員向け電子書籍サービス「電子図書館まなびライブラリー」の読書履歴データをもとに、読書が子どもの学習や生活におよぼす影響を調査・研究。
同研究所では、進研ゼミの会員向け電子書籍サービス「電子図書館まなびライブラリー」の読書履歴データをもとに、読書が子どもの学習や生活におよぼす影響を調査・研究。
今回は、過年度までの研究を踏まえ、読書が国語の知識や思考力といった多様な資質・能力の形成にどのような効果を持つのかを検証するために、小学5年生から6年生の1年間にわたる「読書履歴データ」と「実力テストの結果」に加えて、「アンケート調査」を組み合わせた分析を行った。
それによると、本を多く読んでいる子どもほどテストの偏差値の変化にプラスの効果があった。
その傾向は、漢字や文法などの「知識問題」だけでなく、思考力を問うような「読解問題」(物語文・説明文の読解)や「挑戦問題」(日常生活場面での問題解決)のいずれにおいても同様にみられた。
つまり、読書の量(冊数)は、国語の「知識」と「思考力」のいずれの力にもプラスの効果があることが分かった。
また、本を多く読んでいる子どもほど「最初から最後まできちんと読む」「気になったところを読み返す」「登場人物の気持ちになりながら読む」など、読み方を工夫していた。
本を多く読んでいる子どもは、「長い文章を読めるようになった」「新しいことを知ることができた」「興味のあることが増えた」「知っている漢字や言葉が増えた」など、自分でも読書の効果を実感していた。
さらに、本を多く読んでいる子どもほど、本を読んでいて「時間がたつのを忘れるくらい夢中になる」「心が落ち着く」を肯定する比率が高い。
コロナ禍で心の健康について報じられる機会が増えているが、読書は、楽しみを広げ、気持ちの面でも大切な存在となっていることが分かった。
同研究所では、2018年度に読書の量が算数の学力に与える影響を、2019年度には読書のジャンルが社会科の学力に与える影響を検証し、その結果を発表している。
今回(2020年度)は、国語の多様な資質・能力の形成に読書がどのような効果を持つのかを検証。知識だけでなく、思考力の形成にどのような効果があるかを明らかにするため、国語の実力テストの問題を「知識問題」「読解問題」「挑戦問題」にわけて分析した。
関連URL
最新ニュース
- iTeachers TV Vol.436 千葉県立市川工業高校 片岡伸一 先生(後編)を公開(2024年12月11日)
- 山梨県、2025年度から25人学級を小学校5年生に拡大、26年度には全学年に導入(2024年12月11日)
- GUGA、大阪府と「求職者等へのDX(IT)に関するスキル等の習得を通じた持続可能な就職支援モデルに関する協定」を締結(2024年12月11日)
- 指導要録の「行動の記録」、教職員の96%が「明快な評価ができていない」と回答 =School Voice Project調べ=(2024年12月11日)
- 仕事をしている母親の子どもの方が希望の中学校に合格している =ひまわり教育研究センター調べ=(2024年12月11日)
- LINEヤフー、「Yahoo!検索」で検索結果面に小学校で習う漢字の書き順動画を掲出(2024年12月11日)
- カラダノート、「ママ・パパが選ぶ今年の漢字ランキング」を発表(2024年12月11日)
- 大学就学を支援する返済不要の給付型奨学金「金子・森育英奨学基金」 総額260万円への増額(2024年12月11日)
- ノーコード総合研究所、大阪府立吹田東高校で「ノーコード開発研修」を実施(2024年12月11日)
- Musio ESAT-J通信教育、世田谷区立太子堂中学校と実証実験を実施(2024年12月11日)