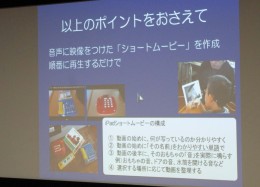2014年1月28日
ソフトバンクモバイルほか/「魔法のランププロジェクト」の成果を教師が語る
東京大学先端科学技術研究センターとソフトバンクモバイル、エデュアスは25日、携帯情報端末を活用した障がい児の学習・生活支援を行う事例研究プロジェクト「魔法のランププロジェクト」の成果報告会を東京・目黒区の東京大学先端科学技術研究センターENEOSホールで開催した。
「魔法のランププロジェクト」は、2013年4月から、特別支援学校・特別支援学級87校に所属する生徒・教員を2名1組にした98組に携帯情報端末の貸し出しを行い、教育現場や日常生活の場での活用を支援するもの。
成果発表会では、6校の教員らが実践事例研究紹介を行い、香川県立高松養護学校 佐野将大教諭ほかは、家庭のニーズに合せてコミュニケーション支援を進めていくための、iPad活用の取り組みを発表した。
高松養護学校は、肢体の不自由な児童らのための特別支援学校。児童らの障がいの状態もさまざまだが、保護者が子どもと日常的なコミュニケーションを図る上で、ときとして支障をきたすケースもあるという。佐野教諭は、そうした際に参考となるiPadによる選択コミュニケーションの実践事例を紹介した。
対象となった家庭ではそれまで、児童の要望を知るために、たくさんの言葉を使って尋ねることがあり、また、児童の反応に対して先読みする傾向があったという。児童も、自分の意思が正しく伝わらないことで、泣いたり叫んだりするようになることがあった。
そこで、これまでのように長いセンテンスでの質問をやめて、「おもちゃの音」「ドアの音」「水筒を開ける音」などと動画をまとめた日常生活に関連するショートムービーをiPadで見せることで、選択肢を提案して待つというコミュニケーションを行った。
すると、動画や音声から知覚・理解し、声を出すようになるといった変化が生まれ、導入前は泣き続ける回数が週に11回もあったが、導入後は週1回程度になるなどの効果があったと語った。
また会場内には、全国の特別支援学校の取り組み内容をポスターセッションとして資料の展示。視覚、聴覚に困難があるケース、知的障がい、自閉症、肢体不自由、重度重複のケースなどに分け、89の事例が紹介された。
魔法のプロジェクトでは、より幅広い支援を目指し、これまで支援してきた特別支援学校・特別支援学級の障がい児に加えて通常学級の発達障がい児にも携帯情報端末を一定期間無償で貸し出し、実践研究を実施する。協力校募集は2月24日まで。
関連URL
最新ニュース
- ヘッドウォータース、東京都教委開催の「モバイルアプリコンテスト2025」を支援(2026年2月20日)
- ラインズ、茨城県龍ケ崎市で入退室管理システム「安心でんしょばと」一斉導入(2026年2月20日)
- 「教育機関の教員に対する生成AIの利用状況に関する調査 2026」協力依頼(2026年2月20日)
- 小中学生の「文系・理系」進路選択、保護者の7割以上が「特に希望はない」と回答 =LUXGO調べ=(2026年2月20日)
- 小学校入学、年長児保護者の84.5%が「不安あり」と回答 =ベネッセ調べ=(2026年2月20日)
- 金沢工業大学とNVIDIA、AI社会実装や高度情報技術者育成で学術連携協力協定締結(2026年2月20日)
- 中央大学、細胞診に即利用できるスタンドアローンAI診断支援システムを世界初開発(2026年2月20日)
- 九州大学、秀逸な若手研究者を採用する「稲盛フロンティアプログラム」第4期公募開始(2026年2月20日)
- 京都芸術大学、通信教育部がバークリー音楽大学・放送大学の一部科目を単位認定(2026年2月20日)
- mikan、西部台千葉高等学校における「mikan for School」導入事例を公開(2026年2月20日)