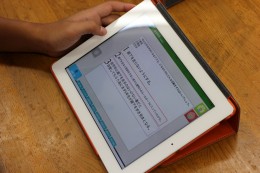2014年11月5日
愛和小学校/タブレット活用研究授業と校内研究協議会を開催
東京都多摩市立愛和小学校は10月31日、「タブレットPCの日常化が拓く新たな教育スタイルの創造」を研究主題とする研究授業「下級生に伝えたいこと~第1回卒業生として~」と、第2回校内研究協議会を開催した。
研究授業は6年生の学級活動として行われたもので、「みんなのお手本となるクラス」になるための活動を決め、意欲的に取り組もうとする気持ちを高めることをねらいとしている。
今時限ではこれまで積み上げてきた「自分たちの課題と克服方法」や「下級生に伝えたいこと」、「学級全員で取り組むこと」などを元に、「どのような活動を行うか決めよう」というのが課題。
ICTの活用としては、はじめに電子黒板で「議題」や「めあて」について竹田晶教諭から説明があり、その後1人1台のiPadと協働学習支援アプリ「Real-time LMS」を使った意見交換へ移行。そして、ロイロノートを使って「自分の意見」、「理由」、「具体的な方法」、「良い点」、ふりかえって「自分の意見」という5枚のテキストカードをまとめ、iPadと電子黒板を使って発表するというものだった。
発表後はiPadを片付け、席をロの字型に並び替えて「どのような活動を行うかを決定する」話し合いを行った。ここでは、意見が二分した「挨拶をしよう」と「廊下を走らないようにしよう」について、議長を決めずに議論が進められた。
「来賓や保護者にちゃんと挨拶できれば、学校の印象が良くなって生徒も増える」という意見の一方、「あいさつしなくてもケガはしない」「お客さんは毎日来ないが、走る子は毎日いる」 等の意見が出され、結果的に「廊下を走らないようにしよう」に決定した。
研究授業後行われた研究協議会は、前回提案のあった「Real-time LMS」を使った意見交換となった。教諭全員がやや戸惑いながらiPadやPCを使って、課題への回答、意見交換などを行った。通常は声の飛び交う協議会だが、一人ひとりがツールに向いアプリを使った協議会風景は、ディスカッションと呼ぶのには、静かすぎる雰囲気だった。
授業を担当した竹田教諭は、「人数が少ないので全員が意見を言う習慣があるが良いか、悪いか」「考えを深めるという事がうまくできない」「普段の人間関係で議論が進み、意見を強く言う者の方向に向かってしまう」と等と、授業を評価した。
最後に、協議会の講師として参加した帝京大学の鎌田和宏教授は、「iPadやアプリは良く使いこなしていたが、それ以前に授業設計の計算も必要。課題の切実さが認識、共有されているかどうか。話し合いをまとめるための指導が行われているか。授業にも事前の根回しが必要。ICTの活用はあくまでかけ算、増幅装置なので、もとの数値がないと成果も大きくならない」と、ICT活用以前の準備も大切だとまとめた。
関連URL
最新ニュース
- 子どものタブレットに遊び以外で期待する使い道ランキング=アタムアカデミー調べ=(2026年2月24日)
- 河合塾、国公立大学2次試験志願状況分析 共通テスト難化で難関大中心に安全志向強まる(2026年2月24日)
- 志望校を下げた私立大学生の6割が「後悔していない」と回答=武田塾調べ=(2026年2月24日)
- 就職会議、「26卒が後輩におすすめしたい企業ランキング」を発表(2026年2月24日)
- 中学受験、保護者の9割以上が「学習以外の悩み」に直面=feileB調べ=(2026年2月24日)
- 外資就活総合研究所、「生成AI時代におけるITエンジニア職志望学生の意識調査(2027年卒)」公開(2026年2月24日)
- 個別指導塾「スクール IE」、「もったいない努力あるある調査」の結果を公開(2026年2月24日)
- コドモン、京都府和束町の公立保育所が保育ICTサービス「CoDMON」を導入(2026年2月24日)
- 通信制「ワオ高校」、2026年度入試「3月出願」の受付を開始(2026年2月24日)
- サカワ、鶴岡市立朝暘第五小学校のワイード導入事例を公開(2026年2月24日)