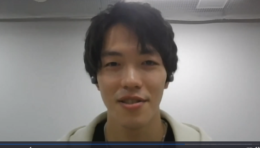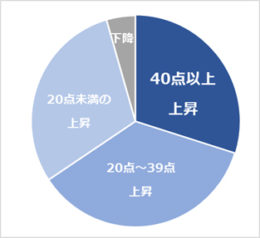2020年12月3日
すららでリメディアル教育が劇的効率化/武蔵野大学
【PR】
大学による学び直し「リメディアル教育」の需要
学校推薦型選抜・総合型選抜(旧 推薦・AO入試)で大学進学する受験生が増加の一途をたどっている。現在、私立大入学者の実に半数以上がこの「推薦・AO組」だ。国立大も、以前は全入学者の3割程度だった推薦・AOの合格者枠を、5割程度まで引き上げた。
こうした傾向は、基礎学力のみで選抜してきた従来の入試への問題意識が生み出している。受験が暗記力勝負の点取りゲームと化し、いわゆる勉強“しか”できない学生を生み出したのではないか、意欲や主体性・多様性・協働性などの非認知能力も含めて、もっと多面的に受験生を評価すべきではないか、との考えだ。2021年度入試からの大学入試改革も同様の趣旨である。
これらの選抜方法は多くの受験生にチャンスを広げたが、一方でこんなケースも生み出した。大学での学修に必要な学力が習得しきれておらず、入学後に苦戦する学生が散見され始めたのだ。そこで大学側が取り組んだのが、主に入学前の期間を使って合格者たちの学び直しを行う「リメディアル教育」である。分かりやすく言えば「補習」だ。
このリメディアル教育、一般的には学力の遅れを取り戻す制度として認知されがちだが、必ずしもそのパターンばかりではない。文理融合型など学生層が多様な大学・学部において、最低限必要な基礎知識の土台を揃えるためにも用いられる。武蔵野大学工学部環境システム学科(東京都)もその一校だ。
文理融合学科ならではの悩み
同学科は、世界の環境問題に関する研究を行っている。名前からは典型的な理系の印象を受けるが、環境問題はサイエンスだけでは解決できない分野だ。経済学や政策学なども含めて、学際的に横断しながら学ぶ必要がある。そのため同学科は文系出身者も一定数おり、入試も国語と英語の2科目で受験したという学生も少なくない。
学科長の明石修准教授は言う。「文理融合で多様な学生がいることは本学科の魅力ではありますが、やはり専門性の高い学びに入っていくには、数学・理科で最低限押さえておいて欲しいレベルがあります。ここがクリアできていないと、スタートラインが揃わないのです」。
そのため同学科では以前から、学生の現有学力に基づいて4つのクラスに分け、物理・化学・数学のリメディアル教育を実施。習熟度別のサポートを行っていたが、完全に対応できていたわけではなかった。嘆息まじりに明石准教授が明かす。
「4段階の分け方では不十分だったのでしょう。ついて行くのに苦労する学生もいる一方で、『なぜ今さらこんなことを』と感じる学生もいます。私たち教員も、せっかく大学で教鞭を取っているのですから、より専門性の高い学びを早く学生に届けてあげたいのに、それができない。誰もハッピーにならない状況に頭を抱えていました」。
『すらら』導入で、長年のジレンマを解消
4つのクラスをさらに細分化し、個別最適化すれば問題は解決するのだろうが、大学側の人員にも限りがある。ましてや、高い専門性を持つ教員陣に高校の復習を担当させていたのでは、人的資源の無駄遣いも甚だしい。やらねばならないのにできない、そんなジレンマに陥っていたが、そんな同学科を救ったのが、ICT教材の活用だった。
導入したのは『すらら』(すららネット提供)。
アダプティブな機能が人気の無学年式オンライン教材だ。学習者の理解度や誤答の原因などを自動で判断し、それに基づき、出題形式なども同じく教材側が自動でアレンジしてくれる。
また、進捗の可視化や弱点の対策フィードバックも可能だ。同学科が求めていた「個別最適化」において無類の強みを持つ教材だったと言えよう。出題から分析、その後のフォローまで教材がワンストップで行ってくれるのだから、そこに教員のマンパワーを割かなくて良い点も大きな魅力だった。
チューター制度を登用し、先輩・後輩双方に成長をもたらす
すららの導入により、当面の課題は解決の兆しを見せたが、明石准教授らはここからさらに発展的応用を見せた。同学科で以前から導入していた『スチューデントアシスタント(SA)』を、すらら運用のチューターに登用したのだ。
SAは同学科の有志学生らで構成される。「アシスタント」の名前が示す通り、講義などのサポートを行う存在だ。以前はチューター業務を行っていなかったが、すらら導入に伴い実験的に運用してみたところ、これが大当たりした。
具体的な運用方法は以下の通り。まず、学生らは学習の到達目標を立て、すららで演習を重ねていく。定期的にテストを実施(これもすららが出題)し、合格すればリメディアル学習は卒業だ。SAはGoogle Classroomを用いて後輩学生らに履修範囲を指示したり、取り組みを促したり、質疑応答の対応などに当たる。
実際にSAを務めた田代大智さん(3年)は、このように動機を語る。「実は将来、理科の教員を目指していて、オンライン授業や教材がどんなものか知りたかったのがきっかけです。いかに後輩たちのモチベーションを上げながら取り組ませるかは苦労しましたが、これらの経験はきっと教員になったときに活きると思います」。
同じくSAを務めた関優太さん(3年)も、手ごたえを感じていると言う。「教える側に立って、初めて授業準備の大変さや、マネジメントの重要性を理解できました」。
SA学生らに思わぬ成長をもたらしただけでなく、新入生らは不安なく大学での学びに取り組める。もちろん教員陣は、自らの専門分野の研究・指導に全力を注ぐことができ、まさに“一石三鳥”だ。
「本学科のような、学びの多様性に特徴がある大学ほど、こうしたツールをどんどん取り入れるべきだと感じます。基礎的なところはオンラインで行い、対面でワークやディスカッション、PBLにどんどん時間を投じればいい。これまで大学の講義はマスの印象が強かったですが、これからはもっと個別化していくのではないでしょうか」と未来予想する明石学科長。
ICTは、「新しい大学」の在り方にも、その可能性を示している。
関連URL
最新ニュース
- 漢検協会とベネッセ、初コラボ 進研ゼミ会員の小・中学生が選ぶ「今年の漢字」(2024年12月13日)
- AI型ドリル搭載教材「ラインズeライブラリアドバンス」が「高知家まなびばこ」とデータ連携開始(2024年12月13日)
- コドモン、広島県三原市の保育所等13施設にICTサービス「CoDMON」導入(2024年12月13日)
- 陸前高田市、返済不要の給付型奨学金事業の資金調達で1600万円の目標金額達成(2024年12月13日)
- ライフイズテック、中高生向け「ライフイズテック スプリングキャンプ2025」春休み開催(2024年12月13日)
- サイバー大学、「Times Higher Education Online Learning Rankings 2024」でブロンズ評価を獲得(2024年12月13日)
- プログラミングスクール受講生で最も多い年代は20代、平均年齢は33.8歳=「 CloudInt」調べ=(2024年12月13日)
- 不登校・行き渋りの子どもがいる親1000名へのアンケート調査 =サイボウズ ソーシャルデザインラボ調べ=(2024年12月13日)
- 大阪大学、デジタル学生証・教職員証の提供を2025年1月にスタート(2024年12月13日)
- 「デジタルハリウッドSTUDIO」STUDIO渋谷、AIクリエイティブデザイン講座を開講(2024年12月13日)