2022年3月7日
高知高専5年生の論文が『Chemistry – A European Journal』誌のHot Paperと表紙に選出
高等専門学校機構は3日、高知工業高等専門学校ソーシャルデザイン工学科新素材・生命コース5年の野並玲奈さんと白井智彦講師らの研究グループが、イリジウム触媒を用いて医・農薬の開発に有用な光学活性キラル分子の新しい合成方法を確立したことを発表した。
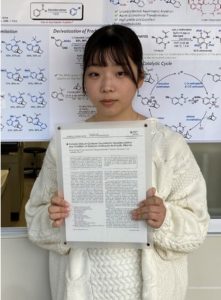
高知高専5年生の野並さん
同研究成果は、1月28日公開のChemistry – A European Journal誌(欧州化学会誌)に掲載され、同誌のHot Paper(同誌の編集者が特にその重要性を認めた論文)およびFront Cover(表紙)に選出された。
右手(実像)と左手(鏡に映る像)の関係にある分子は鏡像異性体と呼ばれる。これらの分子は、形が非常に似ているが重ね合わせることはできない。どちらも同じ元素、同じ数の原子で構成されているが、全く別の構造をもつ化合物。
炭素を主として構成される有機化合物では、不斉炭素1と呼ばれる種類の炭素が分子中に含まれると2つの鏡像異性体を生じることが知られている。鏡像の関係にある2つの分子では沸点や融点などの化学的な性質は変化しないが、分子の立体的な形が異なることに起因して、生体内での働き方に大きな影響を及ぼす。
例えば、人工甘味料として知られるアスパルテームの分子にも不斉炭素があり、鏡像異性体が存在する。片方は,砂糖の200倍と言われるほどの甘さを人間に感じさせるが、もう片方には甘さはなくむしろ苦みを感じさせる。生体内での挙動が大きく異なるため、特に医薬品などの開発では、一方の鏡像異性体だけを選択的に創る技術の開発は非常に重要。純粋な片方の鏡像異性体を得るためには、分子中に含まれる不斉炭素の立体的な形を高度に制御する必要がある。この不斉炭素を構築するために反応性の高い試薬が頻繁に用いられるが、反応後に多量の廃棄物を排出してしまうため、代替となる簡便な合成法の開発が望まれていた。
高知高専ソーシャルデザイン工学科新素材・生命コース5年の野並玲奈さんと白井智彦講師らの研究グループは、反応性の高い試薬を使わずに不斉炭素の形を制御し、一方の鏡像異性体のみを高純度で合成する新しい方法を開発した。反応によって生じる試薬由来の廃棄物は一酸化炭素だけであり、同研究によって様々な構造の有用化合物を簡便に合成することが可能になった。
 発表論文の概要
発表論文の概要
論文名:Cationic Iridium-Catalyzed Asymmetric Decarbonylative Aryl Addition of Aromatic Aldehydes to Bicyclic Alkenes (カチオン性イリジウム触媒を用いるビシクロアルケンへの芳香族アルデヒドの脱カルボニル型不斉アリール付加反応)
著者名:Reina Nonami1, Yusei Morimoto1, Kazuya Kanemoto2, Yasunori Yamamoto3, Tomohiko Shirai1 (1高知工業高等専門学校ソーシャルデザイン工学科(新素材・生命コース)、2中央大学理工学部、3北海道大学大学院工学研究院)
雑誌名:Chemistry – A European Journal
公表日(オンライン公開日):2022年1月28日【論文】、2022年2月9日【表紙】、2022年2月10日【Cover Profile】
関連URL
最新ニュース
- 漢検協会とベネッセ、初コラボ 進研ゼミ会員の小・中学生が選ぶ「今年の漢字」(2024年12月13日)
- AI型ドリル搭載教材「ラインズeライブラリアドバンス」が「高知家まなびばこ」とデータ連携開始(2024年12月13日)
- コドモン、広島県三原市の保育所等13施設にICTサービス「CoDMON」導入(2024年12月13日)
- 陸前高田市、返済不要の給付型奨学金事業の資金調達で1600万円の目標金額達成(2024年12月13日)
- ライフイズテック、中高生向け「ライフイズテック スプリングキャンプ2025」春休み開催(2024年12月13日)
- サイバー大学、「Times Higher Education Online Learning Rankings 2024」でブロンズ評価を獲得(2024年12月13日)
- プログラミングスクール受講生で最も多い年代は20代、平均年齢は33.8歳=「 CloudInt」調べ=(2024年12月13日)
- 不登校・行き渋りの子どもがいる親1000名へのアンケート調査 =サイボウズ ソーシャルデザインラボ調べ=(2024年12月13日)
- 大阪大学、デジタル学生証・教職員証の提供を2025年1月にスタート(2024年12月13日)
- 「デジタルハリウッドSTUDIO」STUDIO渋谷、AIクリエイティブデザイン講座を開講(2024年12月13日)










