2017年6月21日
JPRS、教諭の4割弱「情報教育」教材不足の声に教材無償配布
日本レジストリサービス(JPRS)は20日、中学校と高校の「生徒」と「教諭」それぞれ400人を対象に、「インターネット教育に関する実態調査」の調査結果をまとめ発表した。
インターネット上に数限りなく存在するWebサイトでは、「URL(Uniform Resource Locator)」と呼ばれるインターネット上の住所(文字列)が重要な役割を果たす。調査ではまず、生徒に対して「インターネットを利用する際にURLを意識するか」の問いに、「スマートフォンや携帯電話の利用時」は75.5%が意識せず、「デスクトップパソコン・ノートパソコンの利用時」でも69.8%が意識していないことが判明した。
また、「URLの.jpが日本を表すことを知っているか」との問いに、「知らなかった」と回答した生徒が41.5%に達した。このような結果となった要因としては、スマートフォンなどのブラウザーではURLが非表示になるなど、意識する機会が失われていることなどが考えられる。
一方、中学校・高校で「情報教育」を担当する教諭400人へのアンケートでは、教諭の5.6%がメールアドレスやWebサイトのURLを構成する「ドメイン名は授業で教えていない」と回答。18.5%は「インターネットの仕組みを教えていない」とも回答した。
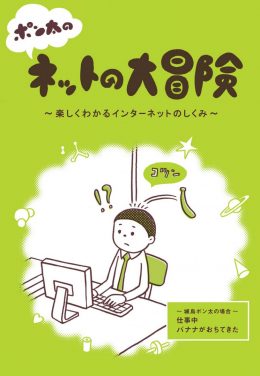 過去5年以内に情報教育の授業を担当したことがある教諭に、授業で使用する教材への満足度について聞いたところ、36.8%が「満足していない」と回答。学校種別で見ると、「教材に満足してしない」と回答した割合は「高校の教諭」が31.5%だったのに対し、「中学校の教諭」は42.0%と10.5ポイント高く、より初歩的な内容を教える中学校での情報教育に使用する教材が不足している実態が明らかになった。
過去5年以内に情報教育の授業を担当したことがある教諭に、授業で使用する教材への満足度について聞いたところ、36.8%が「満足していない」と回答。学校種別で見ると、「教材に満足してしない」と回答した割合は「高校の教諭」が31.5%だったのに対し、「中学校の教諭」は42.0%と10.5ポイント高く、より初歩的な内容を教える中学校での情報教育に使用する教材が不足している実態が明らかになった。
調査時点で「情報教育」を担当している教諭276人に対し、「授業を行うにあたり、自信を持って授業を行えているか」の問いには、「自信を持って教えられている」と回答した教諭はわずか38.4%だった。
同社では、インターネット教育の支援活動の一環として、全国の中学校・高校・高等専門学校を対象に、マンガ小冊子「ポン太のネットの大冒険~楽しくわかるインターネットのしくみ~」を無償で配布している。7月31日(月)まで、教材の配布を希望する教育機関からの申込を専用Webサイトで受けつけている。
関連URL
最新ニュース
- ヘッドウォータース、東京都教委開催の「モバイルアプリコンテスト2025」を支援(2026年2月20日)
- ラインズ、茨城県龍ケ崎市で入退室管理システム「安心でんしょばと」一斉導入(2026年2月20日)
- 「教育機関の教員に対する生成AIの利用状況に関する調査 2026」協力依頼(2026年2月20日)
- 小中学生の「文系・理系」進路選択、保護者の7割以上が「特に希望はない」と回答 =LUXGO調べ=(2026年2月20日)
- 小学校入学、年長児保護者の84.5%が「不安あり」と回答 =ベネッセ調べ=(2026年2月20日)
- 金沢工業大学とNVIDIA、AI社会実装や高度情報技術者育成で学術連携協力協定締結(2026年2月20日)
- 中央大学、細胞診に即利用できるスタンドアローンAI診断支援システムを世界初開発(2026年2月20日)
- 九州大学、秀逸な若手研究者を採用する「稲盛フロンティアプログラム」第4期公募開始(2026年2月20日)
- 京都芸術大学、通信教育部がバークリー音楽大学・放送大学の一部科目を単位認定(2026年2月20日)
- mikan、西部台千葉高等学校における「mikan for School」導入事例を公開(2026年2月20日)











