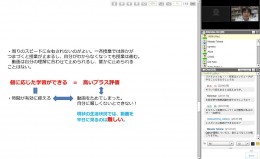2014年7月1日
反転授業の研究/「第10回反転授業オンライン勉強会」を開催
反転授業に取り組む学校が増えている中で、受講する側の生徒たちはどのように感じているのだろうか。反転授業の研究が6月27日に開催した「第10回反転授業オンライン勉強会」では、実際に反転授業を体験した生徒たちの声を紹介した。
勉強会ではこれまで、反転授業の実践するために必要な要素について、学びを深めてきた。第10回は前回に引き続き、「生徒が語る反転授業」をテーマに、第一部で東京国際大学と、奈良女子大学附属中学校の生徒たちの声を紹介。
まず、東京国際大学 商学部経営学科の河村一樹教授が登壇。2013年後期から、自身のゼミの大学1年生を対象にした「アカデミックスキル習得のための演習」で実施している、eラーニングを使った反転授業について解説した。さらに授業の開発・運営を協同で行っている、ハンテンシャの加藤大代表が、授業設計の概要やポイントを紹介。
授業を受けたゼミの生徒からは、eラーニングの活用について、「何を言っているのか分からない先生もおり、そうした授業でも予備知識を入れておけば理解の助けになる」と、肯定的に捉える意見があった。一方、演習について「ある程度の学力が必要になるので、講義形式で基礎的な知識を詰め込んでからの方がいい」と語る生徒もいた。また、事前学習について、「予習をやらないと演習ができない」ぐらいのレベルに設定しないとやる意味がないという声もあった。
奈良女子大学附属中学校の二田貴広教諭は、MOOCを受講した生徒のインタビューを紹介。MOOC提供サイト「gacco」が、4月から6月にかけて実施した「日本中世の自由と平等」(講師:東京大学 本郷和人教授)というコースに、奈良女子大学附属中学校の高校1年生6名が参加。参加生徒は動画で事前学習を行い、2回の対面授業でグループディスカッションとディベートを行った。
動画を使った授業について、肯定的な意見としては、「周りのスピードに左右されないし、分からなければ止められる」「時間を有効に使える」という声があった。しかし、通常の授業のように強制力がないため、「動画をためてしまい、週末にまとめて受けていた」という意見もあり、二田教諭も、高校生の生活状況で動画を平日に見るのは厳しいと補足。そのほかに、動画で予習しているときに、「質問できて、その答えがすぐに返ってきてほしかった」という要望や、「授業をする教員の側も生徒から得るものがあるのではないか」という指摘もあった。
第2部では、オンライングループワークを実施し、参加者どうして学びを深め合った。
関連URL
最新ニュース
- ヘッドウォータース、東京都教委開催の「モバイルアプリコンテスト2025」を支援(2026年2月20日)
- ラインズ、茨城県龍ケ崎市で入退室管理システム「安心でんしょばと」一斉導入(2026年2月20日)
- 「教育機関の教員に対する生成AIの利用状況に関する調査 2026」協力依頼(2026年2月20日)
- 小中学生の「文系・理系」進路選択、保護者の7割以上が「特に希望はない」と回答 =LUXGO調べ=(2026年2月20日)
- 小学校入学、年長児保護者の84.5%が「不安あり」と回答 =ベネッセ調べ=(2026年2月20日)
- 金沢工業大学とNVIDIA、AI社会実装や高度情報技術者育成で学術連携協力協定締結(2026年2月20日)
- 中央大学、細胞診に即利用できるスタンドアローンAI診断支援システムを世界初開発(2026年2月20日)
- 九州大学、秀逸な若手研究者を採用する「稲盛フロンティアプログラム」第4期公募開始(2026年2月20日)
- 京都芸術大学、通信教育部がバークリー音楽大学・放送大学の一部科目を単位認定(2026年2月20日)
- mikan、西部台千葉高等学校における「mikan for School」導入事例を公開(2026年2月20日)