2021年7月1日
明日香、保育業界の「2021年上半期総括と下半期展望」を発表
明日香は6月30日、同社の保育研究プロジェクト「子ねくとラボ」で、保育業界に関する「2021年上半期総括および下半期展望」を発表した。
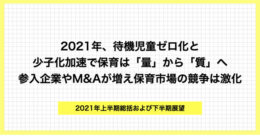 それによると、2021年上半期に、2つの社会的な動きが保育業界に大きなインパクトを与えたという。
それによると、2021年上半期に、2つの社会的な動きが保育業界に大きなインパクトを与えたという。
1つ目は、2021年4月から「新子育て安心プラン」がスタートしたことで、2つ目は、「保育所の利用児童数が2025年にピークを迎える」と発表されたこと。どちらも厚生労働省によるものだが、保育の現場で不安の声が出ているのも事実。
1つ目の「新子育て安心プラン」は、待機児童の解消を目指すとともに、女性の就業率の上昇を踏まえた保育の受け皿整備や、幼稚園やベビーシッターを含めた地域の子育て資源の活用を進めるためのもので、2024年度までの4年間で約14万人の整備を想定。
しかし、2つ目の「保育所の利用児童数が2025年でピークを迎える」ということは、2026年以降は需要と供給のバランスがすぐに逆転しかねない。
つまり、選ばれる保育施設にならなければ施設経営の持続性を失う可能性を示しており、保育施設も「量」から「質」へと変化する視点が欠かせない。この方針転換への布石が、2021年上半期の一大トピックだと言える。
保育業界の市場規模は0.14兆円で、1500億円弱の規模。売り上げ10億円以上の主要企業14社のデータをまとめて他業種と比較すると、160業界中155位で全体から見ると小規模だが、伸び率と利益率は10位以内に入る成長市場。
構造の特殊な点は、保育所でみると経営主体の85%が社会福祉法人で、営利法人による運営は平成29年度では5%程度という点。成長市場ということで新規参入する企業も増えてきているが、いまだ社会福祉法人が多数。
また、2020年から始まった小学校のプログラミング教育必修化や、文科省推進の「EdTech」「STEAM教育」など、時流を反映させながら子どもたちの生きる力を養う教育を国は促進している。
保育所でも、「選ばれる施設」となるために幼児教育をどう取り入れ、いかに利用者にアピールするか、柔軟性や発信力が課題となるが、そこには日々の保育業務に負荷が掛かるのではというジレンマがあることも否めない。
今後取り組むべき事のひとつとしては、未来の保育士を育てる大学の教育学部や養成校と連携し、保育業界の構造や市場規模、そして最新動向を学生に伝えていくという点。
変化と多様性が求められる時代の中、子どもたちが「生きる力」を育めるように保育を行うにあたり、保育士自身が置かれている環境を把握しておくことはかなり重要。
保育所利用児童数が2025年にピークを迎えると報じられ、量より質が重視される中、株式運営の法人やM&A企業のシェアも拡大していく。
これらの企業が、利用者獲得や保育士採用のため、どう差別化に向けた取り組みを展開していくのかが、2021年下半期以降の注目点と言える。
関連URL
最新ニュース
- 漢検協会とベネッセ、初コラボ 進研ゼミ会員の小・中学生が選ぶ「今年の漢字」(2024年12月13日)
- AI型ドリル搭載教材「ラインズeライブラリアドバンス」が「高知家まなびばこ」とデータ連携開始(2024年12月13日)
- コドモン、広島県三原市の保育所等13施設にICTサービス「CoDMON」導入(2024年12月13日)
- 陸前高田市、返済不要の給付型奨学金事業の資金調達で1600万円の目標金額達成(2024年12月13日)
- ライフイズテック、中高生向け「ライフイズテック スプリングキャンプ2025」春休み開催(2024年12月13日)
- サイバー大学、「Times Higher Education Online Learning Rankings 2024」でブロンズ評価を獲得(2024年12月13日)
- プログラミングスクール受講生で最も多い年代は20代、平均年齢は33.8歳=「 CloudInt」調べ=(2024年12月13日)
- 不登校・行き渋りの子どもがいる親1000名へのアンケート調査 =サイボウズ ソーシャルデザインラボ調べ=(2024年12月13日)
- 大阪大学、デジタル学生証・教職員証の提供を2025年1月にスタート(2024年12月13日)
- 「デジタルハリウッドSTUDIO」STUDIO渋谷、AIクリエイティブデザイン講座を開講(2024年12月13日)










