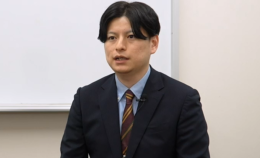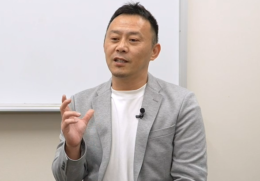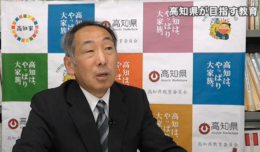2025年3月28日
多様なニーズに応える『すらら』 対話による協働的な学習を通して、深い学びを目指す/高知県立須崎総合高等学校
【PR】
高知県では、令和6年3月に策定された「第4期高知県教育振興基本計画」で、「確かな学力の育成と将来とのつながりを見通した学び」を基本目標の一つに掲げ、「デジタル技術を活用した個別最適・協働的な学びの充実」を推進している。第4期基本計画に先立って、令和4年度から県立高校の一部で『すらら』の活用を進めている。
高知県立須崎総合高等学校数学科の公文教諭、仁木教諭には具体的な授業の進め方について、また高知県教育委員会事務局高等学校課廣瀬企画監には『すらら』導入のねらいと成果について話を聞いた。
多様なクラスのニーズに応じた『すらら』の活用 公文教諭
-御校の特徴と『すらら』活用について教えてください。
「本校は、普通科と工業科が統合して設立された高等学校であり、クラスごとに多様性があります。クラスによって、使用する教科書や授業のレベルも異なるため、それぞれのニーズに合った『すらら』の活用が効果を発揮しています。」
-具体的にどういった場面で『すらら』を活用されていますか?
「授業内でも『すらら』を活用し、テスト前の対策としても頻繁に用いています。普通科の進学コース以外のクラスでは、まず授業内容の理解を確実にするために『すらら』を活用、ある程度定着した段階で書き込み式のワークを用いて仕上げを行うことで、学習効率を向上させています。
一方、進学コースのクラスでは、『すらら』で多くのユニットから網羅的に出題し、教科書とは異なる方式での設問に取り組むことで、多様な問題形式に対応できる力を養っています。その結果、教科書レベルの理解を確実にし、その上で難易度の高い参考書へと挑戦できるようになります。『すらら』は、教科書と参考書の橋渡しとして重要な役割を果たしています。」
-生徒の変化はありますか?
「特に感じるのは、生徒が『楽しみながら』学べているということです。これまで1人でワークに取り組むことが苦手であった生徒も、『すらら』ならクイズ形式のようで楽しいと感じているようです。生徒からは、丸つけが自動で便利、第三者に丸をつけてもらえる感覚が楽しいという声も聞かれました。」
-『すらら』導入の成果はいかがですか?
「私も含め、多くの先生方が、テスト期間のワークとして『すらら』で課題を配信しています。生徒の学習進捗を容易に把握できる点が非常に便利です。
従来の紙のワークでは、わからない問題の解答をそのまま写してしまう生徒もいましたが、『すらら』ではそれができません。正解するまで繰り返し出題されるため、生徒の理解度を正確に把握できます。
今年度導入したばかりのため詳細な分析はこれからですが、定期試験の平均点には導入以前と比べて伸びが見られています。今後さらにデータを蓄積し、分析を進めていきたいと考えています。」
従来からの生徒同士が学び合う数学を『すらら』の活用でさらに効率的かつ効果的に 仁木教諭
須崎総合高等学校では、以前より生徒同士の対話を重視した「学び合うスタイルの授業」を取り入れている。今回、「すらら」を活用し、ICT教材の特性を生かして、その学習効果を高めた。
数学科では、仁木教諭が授業の冒頭で流れをフローチャートで示し、「すらら」を活用して効率的かつ効果的な授業を展開した。
-授業のフローチャートを作るねらいを教えてください。
「今回の『すらら』を活用した数学の授業では、生徒一人ひとりに最適な学びを提供したいと考えました。そのために流れを視覚的に生徒に示すフローチャートを作りました。
スタートでは、『みんなにできてほしい問題』を提示し、つまずきに応じてもう一度復習をしてから問題へと戻るパターンと、新たな知識を確認するための次の問題へと進むパターンに分かれます。次にやるべきことを明確に伝え、スムーズな学習を促すことがねらいです。」
-「学び合うスタイルの授業」について、聞かせてください。
「私が板書し、それを見て学習する一方向の授業だけではなく、生徒同士が問題を解く過程で話し合う機会を多く設けることで、理解を深めます。
私たち教員は数学的な表現を使って説明しますが、中にはそれを難しいと感じる生徒もいます。しかし、生徒同士は自分たちの言葉で話し合うことで、内容をより理解し、精緻化することがよくあります。
ですから、一方向の授業ではなく、生徒たちが協働し理解を深め、さらに正確に知りたい時に教員へ質問できるような授業を工夫しています。」
-活発な質問のために工夫されていることはありますか?
「日常的に、繰り返しこういった授業を展開しているので、習慣化しています。当初は間違うことへの恐れから解答を共有できない生徒もいましたが、正解を最初に提示せず、あえて正誤がわからない状態にすることで会話しやすい状況を作りました。」
「すらら」で学ぶ生徒の皆さんの活用法・感想 普通科2年生
-生徒同士で学び合う授業で、実際に『すらら』を活用していかがでしたか?
「友達と話し合い、コミュニケーションを取りながら問題を解くという時に、『すらら』だととても活用しやすいと感じました。」
-『すらら』の活用法や率直な感想、意見を聞かせてください。
「テスト前に使っています。数学の場合、教科書の問題だけだと1つの導き方しかありませんが、『すらら』は多くの問題や解答方法があるので力がつきます。特に『すらら』は応用力がつくと感じています。これまでは基礎問題の学習が多かったのですが、『すらら』で取り組んだことで、知識を活かして、基礎プラス応用で解く力がついたと実感しています。」
「国語・数学・英語を中心に活用し、授業後の休み時間に課題に取り組んでいます。テスト対策としても、先生方が出してくれる『すらら』の課題で学べるため、とても便利です。
『すらら』の活用で勉強時間が増え、苦手な部分も正答率100%になるまで繰り返し取り組むことで、素早く覚えられるようになりました。理解が深まると授業も一層楽しく感じられます。
数学では、難問に多く触れられ、試験の時も『すららでやったな』と思い出し、スムーズに解けるようになりました。また、苦手だった国語の文章問題も、詳しい解説のおかげで少しずつ克服できています。」
「国語と英語を家庭学習で活用し、数学は間違えた問題の復習に取り組んでいます。これまで学校のテストでは、問題集と同じ問題なら解けますが、少しでも違うと解けませんでした。『すらら』で多様な問題に触れ、様々な出題に慣れることができ、効果を実感しています。」
「模試や基礎学力テストに向けて、国語や英語、数学を活用しています。特に数学は、途中式の誤りまで採点して詳しく解説してくれます。間違った場合は、その基礎問題から解き直せるのでとても良いと感じています。」
高知県が推進する「デジタル技術を活用した個別最適・協働的な学びの充実」
『すらら』が果たす役割とは 高知県教育委員会事務局高等学校課廣瀬企画監
「高知県では『第4期高知県教育振興基本計画』に基づき、確かな学力の育成と自己の将来を見据えた学びを進めています。重点を置いている『基礎学力の向上』のため、県は『すらら』を導入しました。
『すらら』は質の高い説明動画と充実したドリル機能を提供し、基礎学力を効果的に向上させると考えています。また、苦手意識を持つ生徒にも、わかりやすい動画や、小中学校の範囲を縦断する幅広い教材が大きな利点です。
『すらら』を活用することで、基礎学力が向上するだけでなく、生徒が主体的に学ぶ姿勢も見られ、家庭学習の定着も進んでいます。『すらら』で配信する課題を家庭で学び、学校で確認できる点にも手応えを感じています。
高知県は、生徒が自身の夢や志を実現できるよう、基礎学力や思考力、判断力、表現力を向上させるため、『すらら』をはじめICTを活用した学びを推進しています。」
関連URL
最新ニュース
- シンシアージュ、大阪・羽曳野市と子どもの学びと地域理解を推進する「包括連携協定」締結(2026年2月25日)
- VLEAP、中高生向け租税教育用デジタル版ボードゲームの制作に協力(2026年2月25日)
- 子どもの習い事、83%の親が「成長に合わせて選び方を変えるべき」=イー・ラーニング研究所調べ=(2026年2月25日)
- 令和の現役高校生は日常的にAIを使う。男女で大きな差 =ワカモノリサーチ調べ=(2026年2月25日)
- サイバー大学、学習歴と身分証を統合する次世代型「スマート学生証」を先行導入(2026年2月25日)
- 大和大学と奈良先端科学技術大学院大学、教育・学術分野の連携推進する包括協定締結(2026年2月25日)
- GMOメディア、ポータルサイト「コエテコbyGMO」で会話型プログラミング教室レコメンド機能の提供開始(2026年2月25日)
- 三英、STEAM教育スクール所属の中高生ロボティクスチームが「3冠」達成(2026年2月25日)
- 未踏社団、小中高生クリエータ支援プログラム「2026年度 未踏ジュニア」募集開始(2026年2月25日)
- ネイティブキャンプ、アプリ開発・起業教育プログラム「Technovation Girls 2026」に協賛(2026年2月25日)