2021年3月16日
ICTで学びを保障する“合理的配慮”シリーズ 第7回 肢体不自由のある子どもたちの生活や学習面での合理的配慮 後編
肢体不自由のある子どもたちの生活や学習面での合理的配慮 (後編)
金森克浩(日本福祉大学スポーツ科学部教授)
前回は、肢体不自由のある子供の困難さと、その子どもたちを生活や学習面で支援するための考え方について紹介しました。今回は、具体的にICTを活用してできることを紹介していきます。
5.コミュニケーション面での支援
前回も書いたように特別支援学校に在籍する多くの肢体不自由の子どもは、からだ全体の機能に麻痺があります。他人との意思疎通として話すことや聞くこと、文字を書いて伝えることなどにも困難さを示します。しかし、人間が生きていく上でコミュニケーションをとることはとても重要です。そこで、ICT機器を活用したコミュニケーション機器を多く活用しています。これまでは、専用の機器が多く使われていましたが、現在はiPadを中心としたタブレットPCにソフトを入れて使われています。
それらは、そのままタッチパネルで操作する子どももいますが、手の麻痺があって押し間違いがおきてしまう場合も多いので、専用のカバーを付けたり、特別な入力装置を外部に付けて操作する場合もあります。
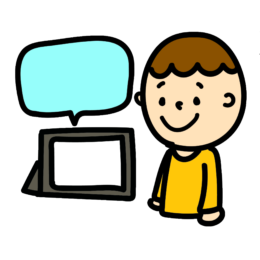 また、コンピュータなどには標準で「アクセシビリティ」という機能が備わっています。これは、操作に難しさを示す人のための補助的な機能で、キーボードを押し続けても1回だけの入力として認識させたり、「Control + ALT + Delete」などのように、いっぺんに複数のキーを押す必要があるものでも、順番に押せば3つ押したことと同じ反応をしてもらえるようにしするなどの機能があります。この他に、画面上の情報をすべて音声で聞こえるようにしたり、逆に音が鳴っているものを、画面で表示するなどの機能もあります。
また、コンピュータなどには標準で「アクセシビリティ」という機能が備わっています。これは、操作に難しさを示す人のための補助的な機能で、キーボードを押し続けても1回だけの入力として認識させたり、「Control + ALT + Delete」などのように、いっぺんに複数のキーを押す必要があるものでも、順番に押せば3つ押したことと同じ反応をしてもらえるようにしするなどの機能があります。この他に、画面上の情報をすべて音声で聞こえるようにしたり、逆に音が鳴っているものを、画面で表示するなどの機能もあります。
このように、一般の製品の中にも合理的配慮を実現するための機能が入っていることをあらかじめ知って上手に使いこなせれば、操作に困難がある人を支援できるのです。
6.ICTを活用することでできること。
 GIGAスクール構想で、すべての学校にひとり1台のタブレット端末が導入されれば、教科書はタブレットの中に入ります。手を大きく動かさなくても、タブレットの上で指を軽く滑らせれば文字を書ける子どももいます。鉛筆が持てなくてもキーボードやマウスを操作できれば文字を入力することや線を書くとも簡単です。環境側が変わることで、それまで参加できない子どもがともに学べるようになるのです。
GIGAスクール構想で、すべての学校にひとり1台のタブレット端末が導入されれば、教科書はタブレットの中に入ります。手を大きく動かさなくても、タブレットの上で指を軽く滑らせれば文字を書ける子どももいます。鉛筆が持てなくてもキーボードやマウスを操作できれば文字を入力することや線を書くとも簡単です。環境側が変わることで、それまで参加できない子どもがともに学べるようになるのです。
また、もう一つメリットは、多くの人とのコミュニケーションが図れることです。昨年はコロナの影響があってすべての子どもたちが学校に通うことができなくなりました。現在もまだ予断を許さない状況ですが、いずれは収束に向かうでしょう。そんな中で、多くの学校では家庭とリモートでつながり、遠隔学習をしていましたね。実は、肢体不自由のある子どもの多くは、コロナが無いときも学校に通うことに困難がありました。自宅に先生が来ての訪問授業や、病院に入院しての院内学級での授業などを受けている子どもなどです。
 彼らは、たとえコロナが収束したとしても気軽に外に出ることは難しいのです。そこで、リモート会議で今やられていたようなシステムを活用した学習やコミュニケーションが、インターネットが普及した四半世紀前からおこなわれていました。特別支援教育は遠隔学習の先駆けだったともいえます。そして逆に、今多くの場所でやれれている遠隔学習のノウハウは、肢体不自由のある子どものこれからの学習にきっと生かされると考えています。
彼らは、たとえコロナが収束したとしても気軽に外に出ることは難しいのです。そこで、リモート会議で今やられていたようなシステムを活用した学習やコミュニケーションが、インターネットが普及した四半世紀前からおこなわれていました。特別支援教育は遠隔学習の先駆けだったともいえます。そして逆に、今多くの場所でやれれている遠隔学習のノウハウは、肢体不自由のある子どものこれからの学習にきっと生かされると考えています。
7.障害の重い子どもの支援機器
現在のタブレットPCなどの機器の操作では、画面をタッチすること、キーボードを操作すること、マウスを操作することが中心となります。しかし、筋ジストロフィーと呼ばれるような、筋肉の力が徐々に弱まる病気になると、それらも難しくなります。しかし、スマートスピーカーのように、音声で操作できる機器があれば、声だけでも操作が可能になります。
また、専用の外部機器を用意すれば、僅かな指の動きを入力に変えてスイッチ1つでパソコンの操作ができるようになります。有名なのは、ホーキング博士の使っていたコンピュータなどです。実は、皆さんが使っているパソコンやスマホ、タブレットPCには、前述のアクセシビリティ機能に、ホーキング博士が使ったのと似たような、スイッチ1つで動かせる機能が備わっているのです。
 また、近年はそういったスイッチ操作だけでなく、視線マウスと呼ばれる機能でパソコンが使えるようになってきました。そうなれば、直接パソコンに触れることなく、さまざまな事ができるようになります。私の知っているある小学生は、視線だけで様々な学習をし、プログラミングなどもします。また美術展では視線の書道で表彰されていました。
また、近年はそういったスイッチ操作だけでなく、視線マウスと呼ばれる機能でパソコンが使えるようになってきました。そうなれば、直接パソコンに触れることなく、さまざまな事ができるようになります。私の知っているある小学生は、視線だけで様々な学習をし、プログラミングなどもします。また美術展では視線の書道で表彰されていました。
8.まとめ
肢体不自由のある子どもたちの生活や学習を豊かにするためには、支援機器と呼ばれるさまざまな機器は欠かせません。その中でも、ICT機器は大きな役割を果たすと考えます。しかし、気をつけなければならないのは、機器ありきになってしまうことです。大切なことは、子どもたちが何をしたいかを確認することです。学校は、教育の場であると同時に、子どもたちの学びの場です。教える側に立つのではなく、学ぶ立場の子どもたちが何を求めているかを考えてICTを使うようにしてください。
 《執筆者プロフィール》
《執筆者プロフィール》
金森克浩
日本福祉大学教授
金森克浩(日本福祉大学スポーツ科学部教授)
特別支援教育士スーパーバイザー。福祉情報技術コーディネーター1級。
文部科学省「教育の情報化に関する手引」作成検討会構成員。文部科学省新しい時代の特別支援教育の在り方に関する有識者会議委員。文部科学省「障害のある児童生徒の教材の充実に関する検討会」委員。NHK for School「ストレッチマン・ゴールド」番組委員。
主な著書に、「発達障害のある子の学びを深める教材・教具・ICTの教室活用アイデア」(明治図書)「〔実践〕特別支援教育とAT(アシスティブテクノロジー)第1集〜第7集」(明治図書)「知的障害特別支援学校のICTを活用した授業づくり」(ジアース教育新社)「決定版!特別支援教育のためのタブレット活用」(ジアース教育新社)「特別支援教育におけるATを活用したコミュニケーション支援」(ジアース教育新社)他多数。
kintaのブログ
シリーズ記事
ICTで学びを保障する“合理的配慮”シリーズ 第6回 肢体不自由のある子どもたちの生活や学習面での合理的配慮(前編)
ICTで学びを保障する“合理的配慮”シリーズ 第5回 「子どもたちを取り巻くゲーム環境の特徴と配慮点②」
ICTで学びを保障する“合理的配慮”シリーズ 第4回 「子どもたちを取り巻くゲーム環境の特徴と配慮点①」
ICTで学びを保障する”合理的配慮“ 第3回『オンライン教育がもたらすインクルーシブ教育の新しい可能性』
最新ニュース
- ヘッドウォータース、東京都教委開催の「モバイルアプリコンテスト2025」を支援(2026年2月20日)
- ラインズ、茨城県龍ケ崎市で入退室管理システム「安心でんしょばと」一斉導入(2026年2月20日)
- 「教育機関の教員に対する生成AIの利用状況に関する調査 2026」協力依頼(2026年2月20日)
- 小中学生の「文系・理系」進路選択、保護者の7割以上が「特に希望はない」と回答 =LUXGO調べ=(2026年2月20日)
- 小学校入学、年長児保護者の84.5%が「不安あり」と回答 =ベネッセ調べ=(2026年2月20日)
- 金沢工業大学とNVIDIA、AI社会実装や高度情報技術者育成で学術連携協力協定締結(2026年2月20日)
- 中央大学、細胞診に即利用できるスタンドアローンAI診断支援システムを世界初開発(2026年2月20日)
- 九州大学、秀逸な若手研究者を採用する「稲盛フロンティアプログラム」第4期公募開始(2026年2月20日)
- 京都芸術大学、通信教育部がバークリー音楽大学・放送大学の一部科目を単位認定(2026年2月20日)
- mikan、西部台千葉高等学校における「mikan for School」導入事例を公開(2026年2月20日)












